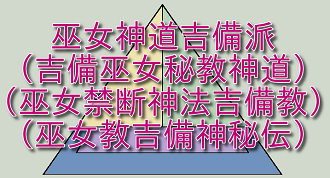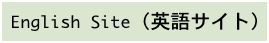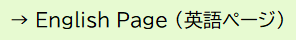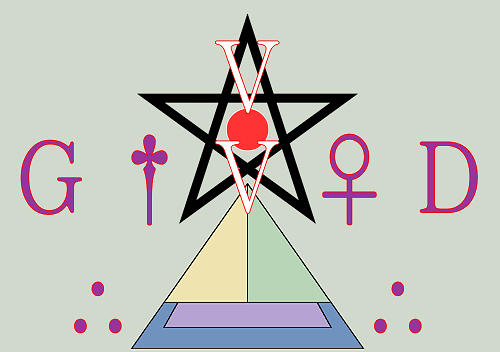【1】巫女弾圧の歴史
巫女弾圧の歴史



■私たちは、下記の三段階の巫女弾圧・迫害策により神道史上はすでに存在していないとされる巫女神道の巫女と、その秘教神道を継承する男性から成る、太古神道研究グループです。
◆第一次・第二次巫女禁断令(1873年)
・・・全国の巫女神道に対し、教部省達として公式に発令。吉備の巫女(私たちの曾祖母や祖母)が屈服せず、吉備の男子シャーマン教・神職教(黒住教、金光教、神習教など)や海外の神秘教団(キリスト教神秘主義、カバラ教団、セレマ神秘主義など)と結託。明治政府(薩長土肥藩閥)は、神道史・古代史の観点では、これを「天皇・ヤマト王権・大和朝廷」対「古代吉備王国」の最終決戦と捉え、王政復古・祭政一致は吉備(および出雲)の打倒により完成すると考えるようになる。政府は、高浜清七郎一派はじめ吉備の伯家神道などを、引き続き京都・東京・宮中から排除。
◆第三次~第十次巫女禁断令・巫女掃討作戦(1874~1945年)
・・・政府は、吉備(他は出雲、信州、恐山)の巫女村に対し、吉備の傀儡神職・県知事を利用し、神社局長に連続で任命して、集中的に監視・破壊。出雲に対しても祭神論争で勝利。出雲巫女神道は、政府からも出雲大社からも離れ、吉備の巫女神道に流れる。全体主義憲法の色彩が濃かった帝国憲法でさえ信教の自由を保障していた中、政府は神社非宗教論の論法に基づき、「国家神道(神社、神社神道、国民道徳)」と「教派神道(宗教神道)」の区分を考案。「国家神道」は宗教ではないため国民に強制できるものとして、事実上の神道国教化を実現させた。
◆戦後
・・・GHQにより神道の国家管理が廃止されたが(神道指令)、依然として吉備派の説(下記)を次の公権力や宗教団体は否定し、巫女たちに主張・思想の発表を行わないよう警告。
(政府、宮内庁、文科省、文化庁、神社本庁、伊勢神宮、岡山県神社庁、神道政治連盟、日本会議、新しい歴史教科書をつくる会など。)
●所属する黒住教、金光教、神習教などの本部や信者からも(単に神社本庁などとの良好な関係を維持したいという意味で)異説の遠慮を推奨するお達しはありますが、これらの教団にも教派神道系教団としての矜恃があり、必ずしも国家神道・神社神道の言いなりにはなっていないため、私たち所属巫女の超教団活動は概ね許されています。